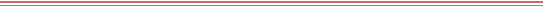 |
|
| |
通過の眼差し「駅 2006」は2002年に東京ステーションギャラリー主催の「東日本―彫刻展」を引き継ぐ彫刻の展覧会です。
東京ステーションギャラリーは2006年4月から東京駅保存復元工事に伴い5年間、休館をします。その間も2011年春の再オープンに向けて美術館活動は継続します。本展は、東京を飛び出し、JR東日本の仙台駅に発表の場を求め、将来を担う若手芸術家4人の協力を得て、駅という開かれた“場”がどう生まれ変わるかの実験をする試みです。 |
| |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
展覧会概要 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 美術館やギャラリーでは鑑賞者が美術作品を見るために出向くので、展示されているものは美術作品と認識されます。しかし、駅では鑑賞者が別の目的で通りかかった時に作品と出会う、まったく新しい、作品と鑑賞者の関係が生まれることになります。本展はこの新しい関係を顕在化させ、美術の社会的役割を探ることを目的とします。駅は、目的地ではありません。目的地へ行くための中継点であり、目的地へ向かう鉄道の発着地です。ここに集まる人たちは常に留まらず通過するだけです。留まるのは待つ時で、そのひと時に目的ではないことを行います。たとえば、駅舎の中を歩き、本を立ち読みし、買い物をします。またトイレに立ち寄ったり、ベンチに座ってコーヒーを飲んだりします。では、鑑賞者となる人々は日頃何を観ているのでしょうか?私たちは目覚めている時、必ず何かを見ています。そして目的にそって目線は動きますが、時には目線は目的から外れたものを見ることがあります。そして、この何気なく見たものがそのひとの心に触れることがあります。このことが非日常へと化し、この一瞬の非日常がまさにその人に自分自身のことを気付かせることになるのではないでしょうか?美術は、私たちを非日常へ誘うことであるならば、この頃美術館に行くことすら日常と化していることを考えると、駅を通過する人たちがまさにその駅で目的からずれたことに出会うことこそ新しい美術展となり、美術社会での役割を考える機会となることを願っています。「旅」の意味にも繋がることです。 |
| |
|
 |