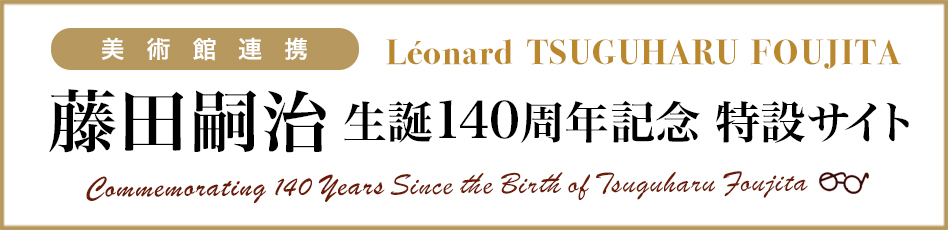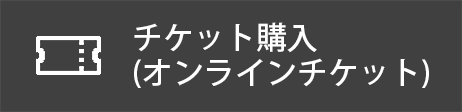Exhibition Overview 展示概要
藤田嗣治(1886-1968)は、乳白色の下地に描いた絵画で世界的に知られた、エコール・ド・パリを代表する画家です。そんなフジタの芸術を「写真」をキーワードに再考する展覧会です。
本展では、画家と写真の関係を次の3つの視点から紐解きます。
1)絵画と写真につくられた画家
フジタは時代の寵児として多くのメディアを賑わせましたが、そのアイコニックな風貌を世に知らしめたのは、何度となく描かれた自画像や繰り返し複製され流通した自身の肖像写真でした。それらは、極東からパリへやってきた無名の画家が世界の第一線に躍り出るために講じた、巧みな「メディア戦略」だったといえるでしょう。フジタが自分自身を描写した絵画と写真を通して、「見られたい自分」をつくり出し、セルフブランディングしていくプロセスを跡付けます。
2)写真がつくる絵画
多くの画家がそうであったように、フジタもまた写真を絵画制作に活用しました。フジタは旅先でスケッチの代わりに写真を使い、世界のあらゆる風景や人々の姿を記録しました。そして写り込んださまざまな細部は、必要に応じて写真から切り出され、数多の絵画作品へと転用されていきました。本展では絵画に現れた写真の断片を探り当て、フジタの写真活用のプロセスを検証します。
3)画家がつくる写真
いくつかのカメラを所有していたフジタは、生涯にわたって数千点におよぶ写真を残しました。華やかなパリ、情緒ただようラテンアメリカ、活気あふれる北京、そして日本。世界中を旅したフジタの写真は、彼の絵画に勝るとも劣らない魅力を備えています。本展では、日本とフランスに所蔵されているフジタの写真の中から珠玉のスナップショットを厳選。フジタの感性を知る“もうひとつの入り口”として、彼が手がけた写真を紹介します。
描くこと、そして撮ること。ふたつの行為を行き来した「眼の軌跡」を追いかけ、これまでにない角度から藤田嗣治の魅力を紹介します。
Highlights みどころ
絵画と写真でセルフブランディング 画家フジタのメディア戦略
オカッパ頭に丸メガネ、口元の髭と奇抜なファッション、そして傍らには猫――。知らず知らずのうちに、私たちはフジタの「イメージ戦略」にハマっていたのかもしれません。画家・フジタを知る人にとってお馴染みのいでたちは、絵画と写真によって、繰り返し再生産されてきました。アイコニックなキャラクターを世に知らしめた自画像とポートレート写真を一挙に展示。映像が氾濫する時代に先駆けた「画家のメディア戦略」の跡を追います。
過去最大級! フジタが撮影した珠玉の写真が一堂に
日本とフランスに遺された数千枚の写真資料の中から、フジタが撮影した優品を厳選して紹介します。愛機・ライカを手にしたフジタは、ひとりのアマチュア写真家として、好奇心の赴くままにシャッターを切りました。1930年代に世界を旅する中で撮られたモノクロ写真と、1950年代のヨーロッパを撮った彩り豊かなカラー写真。いずれも観る者の心を惹きつける必見のスナップショットです。本展はそんなフジタの写真を過去最大級のボリュームで展示する、またとない機会です。東京ステーションギャラリーの赤レンガ壁を背景に、プロの写真家をも唸らせたフジタの写真を存分に味わいます。
徹底比較、絵画と写真 傑作に隠された秘密に迫る
鉛筆や木炭をカメラに替えて、フジタは絵画の素材として写真を活用していました。一期一会の出会いを逃さないように、フジタは旅先のあらゆる景色や人々にレンズを向け、その姿を記録しています。そして、メモのごとく無造作に撮られた写真の一部――人の相貌、衣服の模様、建築、動物など――を切り出しては、キャンバスの上に構成していきました。作品然とした見事な写真を手がける一方で、フジタは画家として、こうした実用的な写真の使い方も実践していたのです。本展では、代表作とその素材となった写真を併せて展示します。絵画それ自体を味わうのは勿論、写真と比較した分析も面白い“一度で二度おいしい”鑑賞が楽しめます。
Sections 章立て
- プロローグ:眼の時代
- 1:絵画と写真につくられた画家
- 2:写真がつくる絵画
- 3:画家がつくる写真
- エピローグ:眼の記憶/眼の追憶
Information 基本情報
- 入館料
-
一般(当日)1,500円 高校・大学生(当日)1,300円
一般(前売)1,300円 高校・大学生(前売)1,100円- *中学生以下無料
- *前売期間は2025年6月1日から7月4日まで、オンラインチケットで販売
- *障がい者手帳等持参の方は入館料から200円引き(介添者1名は無料)
- *学生の方はご入館の際、生徒手帳・学生証をご提示ください
- チケット購入
-
[チケット販売場所]
- ・オンラインチケット
- ・東京ステーションギャラリー1階入口
- *事前にオンラインチケットをご購入いただくと入館がスムーズです
- *サービス券や会員証のご提示で割引をご希望の方は、美術館でチケットをご購入ください。ただし混雑時は入館をお待ちいただく場合があります
- 主催
- 東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団)
- 協力
- レオナール・フジタ財団、メゾン=アトリエ・フジタ(フランス・エソンヌ県)
- 企画協力
- キュレイターズ
- 協賛
- T&D保険グループ