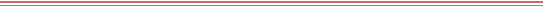 |
|
| |
| 神奈川県立近代美術館の所蔵する油彩約50点を中心に、コラージュや素描約40点、装幀約60点、雑誌の装幀やデザイン関連資料約80点を含め、計約230点で、絵画、名著の装幀、デザインなど幅広く活躍した佐野繁次郎(1900-87)の画家として、またデザイナーとしての魅力をご紹介します。 |
| |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
展覧会概要 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
1900(明治33)年、佐野繁次郎は大阪・船場の老舗筆墨商「古梅園」に生まれました。15歳のときに母に買ってもらった画材で絵を描くようになり、1924年、大阪の信濃橋洋画研究所に入り、小出楢重に師事しました。
1929年には二科展に初入選を果たし、1931年、《休日》で同展樗牛賞を受賞。その頃より、雑誌や本の装幀の仕事を得るようになり、特に横光利一と親しく交流し、横光の著書『機械』をはじめ、生涯に200冊を超える小説や雑誌の装幀を手がけました。
画風の確立を模索しながら、1937年、フランスに渡り、アカデミー・ジュリアンやアカデミー・グランショミエールに学び、マティスに師事。1939年の帰国後は、主に二紀会展に出品をつづけながら、1951-53年、再びフランスに渡り、ミロや金山康喜らと交流しました。
1952年、パリ・トロンシュ画廊で開催した個展は好評を博し、二度目の渡仏は彼に大きな自信を与えました。 画家としての感触を得ていくなか、1955年、銀座名店の広報誌『銀座百点』[(協)銀座百店会発行]の創刊号から1969年7月号まで計176冊の表紙挿絵を担当。都会的な雰囲気と、画面に躍る手書き文字が佐野の個性を印象づけ、当時『暮らしの手帖』を編集・デザインした花森安治にも影響を与えました。
1950年代以降、佐野の絵画には少年っぽさを感じさせる画面構築と色彩がより明確になり、生来の洒脱な感性と個性がいっそう強く反映されました。つねにオリジナリティを意識した自由な姿勢で制作をつづけながら、絵画、装幀、デザインから建物の設計まで幅広く活動した佐野は87歳でこの世を去りました。
本展は、画家としての活動が本格化した1950年代以降の油彩画約50点を中心に、コラージュや素描など約40点、戦前から戦後にわたる代表的な装幀本約60冊、『銀座百点』の表紙絵やデザイン関連資料約80点など、計約230点で構成し、画家として、またデザイナーとしての佐野繁次郎の魅力を紹介します。 |
 |