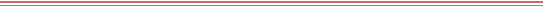 |
|
| |
| 小山田二郎が持つ独特な造型感覚と特異な表現力は、観る人の心を鷲掴みにし鮮烈で衝撃的な印象を与えます本展は日本の戦後美術史の中で50-60年代の時代性と時代を超える普遍性を持った画家としての小山田二郎の回顧展で水彩画を中心にご紹介します。 |
| |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
展覧会概要 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
小山田二郎(1914-1991)は幼い頃に親戚の日本画家・小堀ともと鞆音に透明水彩を学び、父親の反対に会いながらも画家を志望。
1934年、帝国美術学校(現武蔵野美術大学)図案科に入学しました。途中から西洋画科へ転入するものの父親の仕送りを絶たれ中退。その後は流転の生活の中、独立美術協会展や美術文化協会展に出品。戦時体制下はシュルレアリスム弾圧があり一時絵画に絶望をしますが、戦後、再び画家として立つことを決意し、自由美術展を中心に発表をしました。1952年、瀧口修造の推薦によりタケミヤ画廊で個展を開催し高い評価を受けます1959年に団体展に疑問を持ち、自由美術家協会を脱退。以後は画廊での個展を中心に作品を発表しました。
1971年以降は友人にも居場所を知らせずそれまでの家族を残して失踪、社会との関係を画廊に送る作品のみに限るようになります。1991年7月の死も、多くの人は翌年の新聞記事「ひっそりと去った異才―小山田二郎という画家」(針生一郎)で知ることになります。
小山田は自身の身体的特徴と失踪という事件により社会から隔絶することを余儀なくされ、関心は心の内側に向かい記憶の中の幻想や内面の小宇宙を描きました。
その独特の攻撃的・自虐的な造型感覚と表現力は観る人の心を鷲掴みにし、鮮烈で衝撃的な印象を与えます 本展は日本の戦後美術史の中で50-60年代を代表する画家として、またそれを超える普遍性を持った画家として、本来与えられてしかるべき位置付けを再確認しようとする回顧展です。
油彩画38点と水彩画77点、スケッチ資料を展示します。 |
 |