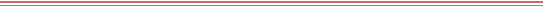 |
|
| |
| 加守田章二(1933−1983)は20世紀後半の日本陶芸界に、異色の才能を燦然と輝かせた陶芸家です。本展では、20世紀をあまりにも早く生き過ぎた加守田章二の作品約180点で、加守田芸術の世界を再認識したいと思います。 |
| |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
展覧会概要 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
加守田章二(1933−1983)は、大阪府岸和田市に生まれ、20世紀後半の日本陶芸界に、異色の才能を燦然と輝かせた陶芸家です。
高校時代から美術の才能を発揮し、京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)に進み富本憲吉教授らのもと研鑚を積みました1956年に卒業後、茨城県日立市の日立製作所関連の製陶所などで働いた後、1959年栃木県益子町に窯を借りて独立し、本格的な作陶生活を始めました。
1961年、鉄釉作品で妻昌子とそろって日本伝統工芸展に初入選したのを皮切りに、1967年には陶芸家として唯一人、第10回高村光太郎賞を受賞しました。
また同年、伝統的な作風からの脱却を考えて日本伝統工芸展への出品をやめ、新しい作陶の地を求めて岩手県遠野市に到達しました。
初めて訪れた遠野の地は加守田にとって制作の弾みになり、遠野に新しい陶房と単窯で修行僧のように制作に励みました。そして、曲線彫文、彩陶など新境地を次々と発表し遠野時代を確立しました。
1974年には、40歳の若さで、陶芸家初の芸術選奨文部大臣新人賞(美術部門)を受賞しました。
デザインを研究し、独創的な器形と加飾を広範に展開していった加守田の作品は、従来の陶芸の概念を超え、多くの人を惹きつけるとともに高い評価を受けました。
また、個展の案内状で「自分の外に無限の宇宙を見る様に、自分の中にも無限の宇宙がある」と述べたように、自らの理想に向かって精力的に作陶を続けましたが、50歳を前に夭折し多くのファンに惜しまれました没後20余年を過ぎても、輝き続ける加守田芸術の世界を約180点の作品で検証します |
 |